 いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
 小学校担任の学級経営の失敗
小学校担任の学級経営の失敗
 いじめについて
いじめについて いじめをうけているあなたへ
いじめをうけているあなたへ いじめをしているあなたへ
いじめをしているあなたへ いじめ被害者とその家族の方へ
いじめ被害者とその家族の方へ いじめ加害者とその家族の方へ
いじめ加害者とその家族の方へ 教師・学校・教育委員会の方へ
教師・学校・教育委員会の方へ 文部科学省の方へ
文部科学省の方へ  いじめ被害者側の対策
いじめ被害者側の対策 いじめの定義
いじめの定義 担任の学級経営の失敗
担任の学級経営の失敗 いじめ問題の責任
いじめ問題の責任 指導という名のいじめ
指導という名のいじめ 部活動での熱中症例
部活動での熱中症例 パワーハラスメント
パワーハラスメント いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案)
いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案) 悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由
悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由 会社におけるパワーハラスメント対策
会社におけるパワーハラスメント対策 虐待を主とした名称変更の必要性
虐待を主とした名称変更の必要性 いじめ自殺は公衆衛生の問題
いじめ自殺は公衆衛生の問題 被害届不受理と少年法廃止
被害届不受理と少年法廃止 私立学校のいじめ対策
私立学校のいじめ対策 続発性の関係嗜癖・依存症
続発性の関係嗜癖・依存症 関係嗜癖と虐待行為
関係嗜癖と虐待行為 関係嗜癖の家族
関係嗜癖の家族 トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ
トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ 公衆衛生・TIC・エンパワメント
公衆衛生・TIC・エンパワメント いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題
いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題 関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ
関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ 心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth)
心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth) トラウマとの闘い
トラウマとの闘い いじめ隠蔽の理由
いじめ隠蔽の理由 第三者委員会での精神科医の報酬と役割
第三者委員会での精神科医の報酬と役割 第三者委員会の問題
第三者委員会の問題
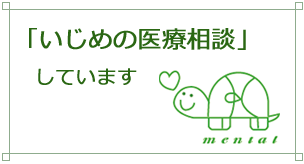
![]() 当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
![]() 【配布用 チラシ】
【配布用 チラシ】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
![]() 【配布用 チラシ②】
【配布用 チラシ②】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
![]() 【参考】
【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
小学校担任の学級経営の失敗
小学校でいじめがあるということ
小学校教諭は、学級経営について学んでいます。小学校の学級経営についての本もたくさん出ています。
それは、学級経営がうまくいくか、いかないかで、その学級の教育の質が決まるからです。
いじめを生まない学級経営が最も大切です。
いじめを起こさないためには、担任教師は、不正に対して毅然とした態度で臨むことが必要です。
文部科学省でも、いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ものであることを十分認識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、適切に対応する必要があるとしています。
- 「弱いものいじめをすることは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと。
- いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。
- いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。
- いじめ問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であること。
- 家庭・学校・地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組む必要がある事。
いじめが起こる学級では、担任教師の「特定の児童・グループの意見ばかり取り入れる。児童の乱暴な発言や不穏当な発言を放置する。児童のルール違反を黙認する。」などの行動が見られます。
「いじめのある場所には、必ず学級崩壊がある」と、『学級崩壊立て直し請負、菊池省三、吉崎エイジーニョ構成、新潮社』という本に書いてあります。
学級崩壊というものには、様々な種類があります。子供たちが表立って大暴れするような崩壊の仕方から、冷戦のように静かに崩壊しているが、保護者は気が付かない状態である時などです。
いじめが遷延する教室の雰囲気は、だいたい似ています。
担任教師は、口先では、「いじめは良くない」と言うこともあります。しかし、担任教師は、人権上、配慮を欠いた言動をしたり、児童の上下関係を肯定・助長するような言動・姿勢をみせたり、いじめに対して妥協・黙認してしまうような姿勢をみせたりします。
つまり、具体的対応や行動はいじめを助長させる行為になっています。
小学校において、いじめ自殺や、あるいは、父兄が知るまでに悪化したいじめ(暴行・恐喝など)は、担任教師が民主的な学級経営に失敗したことを示しています。
さらに、小学校で、恐喝や暴行などの事件が起こっても、担任教師、校長先生が隠蔽すると、警察も事件化を嫌がります。
新聞社やテレビなどのマスコミも、加害者児童の人権があるということで、取り上げてくれません。
中学生、高校生では、学級経営自体の影響は少なく、生徒個々人の性格・人格の影響が強く出てきます。担任教師やクラブ活動の担当教師は、小学校に比べ情報が得にくいため、対応が困難な時があります。また、警察も、新聞社やテレビなどのマスコミも、取り上げてくれるようになります。
このように見ていくと、小学校で嗜癖教育をして、いじめを減らしていくことは重要です。いじめを止めることは、その後の子どもたちの人生を左右する事になります。
自分の心をさまざまの方法で守ろうとする無意識の心理的な作用を「防衛機制」と言います。
「防衛機制」は誰にでも認められる正常な作用です。しかし、仮にも教師と言われる人物が、自分の保身のためにいじめを否認することはあってはならないことです。
否認の仕方には二種類あります。
第一の否認は、「このクラスにはいじめはない!」「いじめ被害者の○○が悪いのだ!」
「行為」そのもの(現実、現状)に理由をつけすり替えて問題がないと思うことです。
自分に非がある担任教師は、自分に不都合なこと(学級経営の失敗)は認めたくないから、否認をします。
第二の否認は、「このクラスはいじめさえしなければ、何の問題もない」
「対象」さえ止めてしまえば問題ないという考えのことです。
総てをいじめのせいにしたいからです。いじめを止めたので一件落着・・・そう思いたいのです。
いじめの原因(学級経営の失敗)を見つめることは、いじめの不始末(いじめ自殺、暴行、恐喝など)を認める事より辛いことかもしれません。「第一の否認」同様、認めないのではなく、認めたくないのです。
いじめをさせないだけでは考え方や行動は変わりません。「いじめをさせなければ問題はない」のですから変える理由はありません。
小学校校長や教育委員会は
「いじめさえなければ、いい小学校教師なんだ」
「学校の力があれば、いじめを止めさせることができる」などと
原因となっている学級経営の失敗に目を向けず、問題の本質(担任教師の学級経営能力の欠如)を認めようとしません。
事実を否認し続けた結果、いじめの問題はどんどん悪化していき、問題の本質(担任教師の学級経営能力の欠如)は放置されます。
早期に介入して、「いじめ問題対応に詳しい補助教員をつける。担任教師を交代する。」などの対処が必要です。
そのようにして、学級経営を正常化させるとともに、被害児童、加害児童、担任教師のそれぞれに適切な、心理教育、治療、再教育などが必要です。


