 いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
 関係嗜癖と虐待行為
関係嗜癖と虐待行為
 いじめについて
いじめについて いじめをうけているあなたへ
いじめをうけているあなたへ いじめをしているあなたへ
いじめをしているあなたへ いじめ被害者とその家族の方へ
いじめ被害者とその家族の方へ いじめ加害者とその家族の方へ
いじめ加害者とその家族の方へ 教師・学校・教育委員会の方へ
教師・学校・教育委員会の方へ 文部科学省の方へ
文部科学省の方へ  いじめ被害者側の対策
いじめ被害者側の対策 いじめの定義
いじめの定義 担任の学級経営の失敗
担任の学級経営の失敗 いじめ問題の責任
いじめ問題の責任 指導という名のいじめ
指導という名のいじめ 部活動での熱中症例
部活動での熱中症例 パワーハラスメント
パワーハラスメント いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案)
いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案) 悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由
悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由 会社におけるパワーハラスメント対策
会社におけるパワーハラスメント対策 虐待を主とした名称変更の必要性
虐待を主とした名称変更の必要性 いじめ自殺は公衆衛生の問題
いじめ自殺は公衆衛生の問題 被害届不受理と少年法廃止
被害届不受理と少年法廃止 私立学校のいじめ対策
私立学校のいじめ対策 続発性の関係嗜癖・依存症
続発性の関係嗜癖・依存症 関係嗜癖と虐待行為
関係嗜癖と虐待行為 関係嗜癖の家族
関係嗜癖の家族 トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ
トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ 公衆衛生・TIC・エンパワメント
公衆衛生・TIC・エンパワメント いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題
いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題 関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ
関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ 心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth)
心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth) トラウマとの闘い
トラウマとの闘い いじめ隠蔽の理由
いじめ隠蔽の理由 第三者委員会での精神科医の報酬と役割
第三者委員会での精神科医の報酬と役割 第三者委員会の問題
第三者委員会の問題
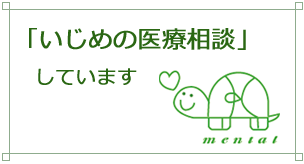
![]() 当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
![]() 【配布用 チラシ】
【配布用 チラシ】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
![]() 【配布用 チラシ②】
【配布用 チラシ②】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
![]() 【参考】
【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
嗜癖
一般的には、アルコール・たばこ・ギャンブル・薬・ゲーム、そして買い物や仕事や性行為など、ある特定の物質や行動、人間関係を特に好む性向のことです。
医学的には、生活などの支障が出てくるまで、「好む性向」に没頭してしまうことをいいます。
嗜癖やアディクションは広義の依存症を指し、「コントロールできない悪い習慣」という意味で使われます。
嗜癖には「物質への嗜癖」「行為への嗜癖」「人間関係への嗜癖」の3種類あります。
「物質嗜癖」とは、アルコール・タバコ・薬物を摂取することに嗜癖することです。
「行為嗜癖」とは、ギャンブル・暴力・万引き・仕事・性犯罪・自傷行為・買い物・インターネット・ゲームなどに嗜癖することです。
「人間関係嗜癖(関係嗜癖)」では、自分の思い通りに相手を動かす事に嗜癖します。思い通りにならない場合に虐待が始まります。
関係嗜癖による虐待行為には、ドメスティックバイオレンス(DV)、児童虐待、パワーハラスメント(パワハラ )、いじめなど、発生する場所により、様々な名称で呼ばれています。
嗜癖と依存症
厚生労働省ホームページの依存症の説明では、以下のようになっています。
医学的定義では、ある特定の物質の使用に関してほどほどにできない状態に陥る状態を依存症と呼びます。
依存症の診断には専門的な知識が必要ですが、特に大切なのは本人や家族が苦痛を感じていないか、生活に困りごとが生じてないか、という点です。
本人や家族の健全な社会生活に支障が出ないように、どうすべきかを考えなくてはなりません。
人が「依存」する対象は様々ですが、代表的なものに、アルコール・薬物・ギャンブル等があります。
素行障害(行為障害)
いじめ加害者は、関係嗜癖ですが、悪化すると素行障害の診断基準を満たすようになります。 素行障害については次の事がわかっています。
・10歳以前に発症を認める小児期発症型の素行障害は男性に多く、攻撃性が強く、成人後も問題を残し反社会性パーソナリティ障害になりやすくなります。
・素行障害の少年の脳活動では、自己制御や理性の部分を司る脳内の部位が反応していないことが示され、利己的・自己中心的な個体保存の衝動的な行動が抑制されません。
・素行障害で臨床紹介された子どもは、84%が大人になっても何らかの精神障害の診断を受け、犯罪行為、身体的な機能障害、社会への不適応などの問題を持っています。
関係嗜癖があると、虐待行為が行われ、被害者にトラウマが出来、複雑性PTSDを発症します。逆に言うと、複雑性PTSDがあるところには、関係嗜癖が存在する可能性がたかくなります。
虐待行為への対応策
関係嗜癖が、問題として発生した環境では、加害者の学習・治療は困難で、加害者の状態が改善するより前に、被害者の虐待死・自殺など取り返しのつかない状態になってしまいます。
そのため、家庭内での虐待行為であるDV、児童虐待では、家庭の中心である加害者から、被害者を保護することにならます。
会社などでは、パワハラ問題で被害者が泣き寝入りをして退職することが多く、問題となっていました。現在は、法的整備がされ、関係嗜癖である加害者が同じ環境にいると、次の被害者が出てしまうため、加害者が異動することになります。
いずれにせよ、被害者を保護し、加害者の虐待行為を物理的に不可能にするため、関係嗜癖である加害者と被害者を引き離して、被害者の安全を確保するのです。
いじめでは、被害者が自殺するか、虐待死するか、不登校なるか、転校をして、物理的に関係嗜癖である加害者との接触が無くなるまで、いじめという虐待行為はなくなりません。
関係嗜癖である加害者を、別の学校に転校させて、いじめ問題を解決する方法を取る学校もあります。
このように考えていくと、いじめ問題が起こらないように学校の環境を整えていくことが重要になります。普段から、いじめ防止教育をして、弱者に居心地の良い環境作りをして、いじめ問題が発生しないようにしなければなりません。
参考文献、図書
こころの科学№.180/7-2015、病としての依存と嗜癖、成瀬暢也
「子どもと青年の素行障害」明石書店、アラン・E・カズン著
「いじめの本態と予防」アルタ出版、岸本朗、後藤百合枝、金子基典、岸本真希子著
厚生労働省、依存症対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html


