 いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
 第三者委員会の問題
第三者委員会の問題
 いじめについて
いじめについて いじめをうけているあなたへ
いじめをうけているあなたへ いじめをしているあなたへ
いじめをしているあなたへ いじめ被害者とその家族の方へ
いじめ被害者とその家族の方へ いじめ加害者とその家族の方へ
いじめ加害者とその家族の方へ 教師・学校・教育委員会の方へ
教師・学校・教育委員会の方へ 文部科学省の方へ
文部科学省の方へ  いじめ被害者側の対策
いじめ被害者側の対策 いじめの定義
いじめの定義 担任の学級経営の失敗
担任の学級経営の失敗 いじめ問題の責任
いじめ問題の責任 指導という名のいじめ
指導という名のいじめ 部活動での熱中症例
部活動での熱中症例 パワーハラスメント
パワーハラスメント いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案)
いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案) 悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由
悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由 会社におけるパワーハラスメント対策
会社におけるパワーハラスメント対策 虐待を主とした名称変更の必要性
虐待を主とした名称変更の必要性 いじめ自殺は公衆衛生の問題
いじめ自殺は公衆衛生の問題 被害届不受理と少年法廃止
被害届不受理と少年法廃止 私立学校のいじめ対策
私立学校のいじめ対策 続発性の関係嗜癖・依存症
続発性の関係嗜癖・依存症 関係嗜癖と虐待行為
関係嗜癖と虐待行為 関係嗜癖の家族
関係嗜癖の家族 トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ
トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ 公衆衛生・TIC・エンパワメント
公衆衛生・TIC・エンパワメント いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題
いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題 関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ
関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ 心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth)
心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth) トラウマとの闘い
トラウマとの闘い いじめ隠蔽の理由
いじめ隠蔽の理由 第三者委員会での精神科医の報酬と役割
第三者委員会での精神科医の報酬と役割 第三者委員会の問題
第三者委員会の問題
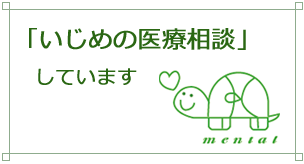
![]() 当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
![]() 【配布用 チラシ】
【配布用 チラシ】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
![]() 【配布用 チラシ②】
【配布用 チラシ②】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
![]() 【参考】
【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
いじめで、自殺念慮がある児童・生徒ための第三者委員会には、精神科医を加えるべきです
一つ目の理由は、心療内科医やカウンセラーは、自殺念慮がある患者を単独では対応しないという事実がある。精神状態が悪くなり、自殺念慮が出てくると、心療内科医やカウンセラーは、転医を進めるか、自分のところだけではなく、精神科も受診するように促す。精神科医は自殺念慮がある患者の対応をする唯一の医師です。
もう一つの理由は過労死やパワーハラスメント受けて自殺した場合、亡くなった後に鑑定書を書くのは、精神科医です。いじめで自殺した場合に、鑑定書を書く場合、精神科医が鑑定書を記載します。
このように、精神的問題で自殺念慮があったり、実際に自殺してしまった場合には、精神科医の判断が求められます。
しかし、いじめが原因で児童・生徒が、自殺しようとした場合にでさえ、第三者委員会に精神科医が参加していないことがあります。これは、社会一般の常識とかけ離れた状況です。
少なくとも、いじめが原因で児童・生徒が、自殺しようとした場合や自殺してしまった場足には、第三者委員会の一人に精神科医を加えるべきです。
委員に精神科医やいじめ問題の専門家を加える場合、弁護士会のガイドラインに基づいて、報酬を決定されるべきです。明らかに低い報酬では、特別な事情がない限り、医師会などは、推薦をすることが出来ません。
第三者委員会の設置およびいじめの対応について、教育長は、スキルトレーニング(知識や技術の伝達)に、重きを置き、テイク・ケア(子どもの動機づけや心理的世話)を蔑ろにしています。
スキルトレーニング(知識や技術の伝達)に、重きを置く教育委員会ではなく、テイク・ケア(子どもの動機づけや心理的世話)を重んじる厚生労働省が対応するべきです。
いじめ問題では、被害者が複雑性PTSDを発症するので、学校、教育委員会、警察は、トラウマインフォームドケアができる体制を整えるべきです。
教育委員会が設立した第三者委員会の設立過程や判定がおかしいと、被害者側からクレームがつき、委員会の再編や、行政庁による判定の変更等が多くなっています。
行政の長によるさらなる再判定委員会が設立され、教育委員会が設立した第三者委員会の異常な判定が多く出ています。
これは、いじめ隠蔽をするような教育委員会が、教育委員会の都合の良い委員を選抜していることに起因します。
行政の長には任命責任があります。いじめ問題が起こった時、教育長とともに行政の長も責任をとるべきです。いじめ問題が解決できない教育長を、継続して、再び任命することは、いじめ隠蔽の擁護をしているとしか考えられません。
行政の長は、教育長を選ぶとき、その人物の情報を議会に早目に提供し、十分な議論の後に、任命するべきです。
教育長は、いじめ関連の法律やガイドラインの都合の良いところだけ使っています。教育長を、任命した行政の長も、その事実を知っていながら容認しています。
そのような行政区では、スキルトレーニング(知識や技術の伝達)に、重きが置かれ、テイク・ケア(子どもの動機づけや心理的世話)を蔑ろにされています。したがって、また同じようないじめ問題が起こると考えます。
コストの問題
第三者委員会を運営するにあたり、委員報酬や交通費、雑費などが発生する。これらの合計金額の概算合計(少なくとも、数百万から一千万円以上になる)を、報告書に載せるべきです。市民や区民の税金から、どうしてそのような支出をしなければいけないかについて、問題提起をすべきです。
教育委員会・学校が、いじめの防止をしていれば、このような多額の支出をしないで済むということを記載すべきです。
いじめ問題の専門家は少ない
いじめ問題に精通している専門家は、ほとんどいません。いじめ問題を掲げている人々はたくさんいますが、実際に解決まで手助けしてくれるところはほとんどありません。
本当のいじめ問題の専門家に依頼する場合、弁護士会のガイドラインにあるように十分な報酬を払う必要があります。
これまでは、優秀ないじめ問題に精通している専門家は、全国でも非常に限られた人数しかいないため、遠隔地での参加が難しい状況がありました。IT技術が進み、新型コロナ対策としてオンライン会議などを活用されるようになりました。遠隔地でも委員や補助員・参考人として参加出来るようになってきています。そのような、全国レベルのいじめ問題の専門家を登録して、活用する組織が必要です。


