 いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
 いじめ自殺は公衆衛生の問題
いじめ自殺は公衆衛生の問題
 いじめについて
いじめについて いじめをうけているあなたへ
いじめをうけているあなたへ いじめをしているあなたへ
いじめをしているあなたへ いじめ被害者とその家族の方へ
いじめ被害者とその家族の方へ いじめ加害者とその家族の方へ
いじめ加害者とその家族の方へ 教師・学校・教育委員会の方へ
教師・学校・教育委員会の方へ 文部科学省の方へ
文部科学省の方へ  いじめ被害者側の対策
いじめ被害者側の対策 いじめの定義
いじめの定義 担任の学級経営の失敗
担任の学級経営の失敗 いじめ問題の責任
いじめ問題の責任 指導という名のいじめ
指導という名のいじめ 部活動での熱中症例
部活動での熱中症例 パワーハラスメント
パワーハラスメント いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案)
いじめ・パワーハラスメント・児童虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)等依存症対策基本法(案) 悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由
悪質ないじめ・パワーハラスメントが無くならない理由 会社におけるパワーハラスメント対策
会社におけるパワーハラスメント対策 虐待を主とした名称変更の必要性
虐待を主とした名称変更の必要性 いじめ自殺は公衆衛生の問題
いじめ自殺は公衆衛生の問題 被害届不受理と少年法廃止
被害届不受理と少年法廃止 私立学校のいじめ対策
私立学校のいじめ対策 続発性の関係嗜癖・依存症
続発性の関係嗜癖・依存症 関係嗜癖と虐待行為
関係嗜癖と虐待行為 関係嗜癖の家族
関係嗜癖の家族 トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ
トラウマ反応・複雑性心的外傷後ストレス障害・震災トラウマ 公衆衛生・TIC・エンパワメント
公衆衛生・TIC・エンパワメント いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題
いじめによるCPTSDの発症と学校側のケアの問題 関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ
関係嗜癖とCPTSD トラウマフォーカスト・アプローチ 心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth)
心的外傷後成長PTG(Post-traumatic Growth) トラウマとの闘い
トラウマとの闘い いじめ隠蔽の理由
いじめ隠蔽の理由 第三者委員会での精神科医の報酬と役割
第三者委員会での精神科医の報酬と役割 第三者委員会の問題
第三者委員会の問題
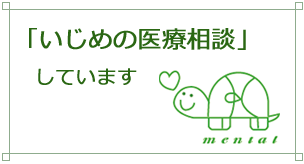
![]() 当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
![]() 【配布用 チラシ】
【配布用 チラシ】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
![]() 【配布用 チラシ②】
【配布用 チラシ②】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
![]() 【参考】
【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
![]() 北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]
3つの問題点
2.自殺問題であるのに、公衆衛生の問題として扱わない。教育行政は公衆衛生の専門家ではない。
3.「緊急ではないが、重要な問題である」ので誰も根本問題に手を付けない。
1. 教育行政の無謬性
日本の教育行政では、ほとんど無意識のうちに前提とされているのが「無謬(むびょう)性の原則」である。「いじめ予防の責任を負った当事者の組織は、いじめ予防が失敗した時のことを考えたり議論したりしてはいけない」という信念です。
例えば、教育長はいじめ予防に責任があるのだから、それが失敗した時(いじめが起こった時)に起きる「いじめ問題解決」について考えてはならない。
もっと極端なことを言えば、教育行政では、「真剣になって、いじめ問題の解決について議論してはいけない」という信念があります。
もし、間違いやミスがあり、教育行政側が謝ったとしても、「いじめ問題の謝罪の会」のように、口先だけ謝って、自分たちは間違っていないと考えています。
2. 公衆衛生の問題
自殺問題は、基本的に教育行政の問題ではなくて、公衆衛生の問題です。
公衆衛生の問題であれば、年単位や数年単位での対応ではなく、一生涯を見つめた対策が必要になります。
また、緊急性は低いが重要な問題であるので、健康問題として厚生労働省が対応するべき問題です。DV(ドメスティックバイオレンス)、児童虐待、パワーハラスメントと同様に、法的整備が必要になっています。
3. 緊急ではないが、重要な問題。理想追求型の問題
本質的な問題は3種類、課題は問題によって異なる
1原状回復型
不具合がすでに顕在化している問題。解決は現状の回復。
いじめ問題があった。いじめ問題がなかった時と同じ状態に戻す。
この方法では、謝罪の会を行っても、いじめが継続する可能性が高い。
理想追求をしないといけない。
2潜在型
放置しておくと不具合の発生する問題。解決は現状の維持。
いじめが起こる前の状態。スクールカーストがある状態。しかし、いじめ問題がいつ発生してもおかしくない状況である。解決は現状の維持ではない。
理想追求をしないといけない。
3理想追求型
現状でも支障はないものの理想を求める問題。解決は理想の達成。
いじめ問題も自殺問題も起きにくい状態。スクールカーストが無く、悪口やモノローグがない状態。対話(ダイアローグ)が出来ており、対等な付き合いが出来る状態(相互尊重)。友達や先生に気軽に相談できる状態。学校が楽しい状態。
足立区立辰沼小学校、仲野繁先生の実践以外は、理想追求型の解決策は見たことがありません。
理想追求型問題の解決
根本課題は、理想を追求するか否かの意思決定
理想追求型問題の解決法の出発点は、そもそも、ある理想を追求するのかどうかです。すでに不具合が顕在化している原状回復型問題、そして、不具合が予測できる潜在型問題では、原状の回復や将来の不具合の予防を追求することが望ましいと、アプリオリに(先天的に)想定されていました。もちろん、そのまま放置しておくことも可能ではあるのですが、それは賢明でないという想定の上、問題解決を考えてきたわけです。
一方、理想追求型問題においては、現状そして将来においても大きな不都合は想定されていません。したがって、放っておいても特に困りはしないことになります。ですから、理想追求型問題の出発点は、理想を追求した方がよいという価値観にあります。
ただし、その過程において、理想追求のコストが極端にそのベネフィットを上回るようであれば、理想追求を断念せざるをえないこともあるでしょう。むろん、まったくギブアップするということではなく、理想を下方修正することによって、コストを下げることも可能であるかもしれません。
いじめ自殺問題は、個々の教育者にとっては、緊急ではないが、重要な問題です。学校現場では「専門的な知識がない、さりとて、それを理解するための勉強時間もない」という状態です。
したがって、学校関係者にとってのいじめ対策は、「専門的でなく、具体的であること」が重要です。
教育者の場合、一年一年を何とか過ごせば、担当する児童・生徒は入れ替わっていきます。数年経てば、異動があります。このように、日々の成績を上げる教育に追われて、個々の教育者がいじめ自殺を止める動機に乏しいのが現状です。
いじめ問題は一生涯の問題となります。一年または数年で、改善していく問題でもありません。小学校や中学校などの教育機関も、児童・生徒たちが数年で卒業しています。教育機関の連携が取れていない状況で、いじめ加害者といじめ被害者の教育・治療は不可能です。また、成長して、DV(ドメスティックバイオレンス)、児童虐待、パワーハラスメントなどの関係嗜癖の問題を起こすかもしれません。
上記を考えると、人の一生を見据えた厚生労働省の対応が必要になってきます。
運営的な課題解決は、4 つの要素を押さえた行動計画
厚生労働省が、いじめ問題の解決するためには、次の4項目を含んだ行動計画の立案を必要をとします。
① 「理想実現の期限の設定」
② 「必要条件の特定」
③ 「スキルや知識の習得」
④ 「実施計画の策定」
時代によって理想も変わる
行動経済成長の時のように、学力向上だけをみていればいい時代はとっくに終わっています。日本は先進国として、子供たちの安全・安心を守るために行動しなければならない時代となっております。
参考文献;問題解決のセオリー、髙杉尚孝、中央精版印刷株式会社
被害者側が出来る最も簡単な方法は、正しい知識を広める方法(啓発)です。
「教育行政の無謬性があり、全能の神のように振る舞い、過ちを認めない。」ような状況でも、「自殺問題であるのに、教育行政は公衆衛生問題として取り扱わない。」状況でも、「緊急ではないが、重要な問題であるので誰も根本問題に手を付けない。」ようなときでも、有効な方法です。
それは、「いじめ問題は、嗜癖・依存症問題であり、治療などの対応をしないと、加害者も被害者も健康被害をうける」ということを、広めることでした。
これも、「いじめ問題という嗜癖・依存症問題を、認知してもらい、嗜癖・依存症問題を知る人が増えることで環境が良くなり、いじめ、パワーハラスメント、DV、児童虐待を無くす。」ということを目的にした理想追求型の問題解決だと考えております。(あくまで、最初の一歩です)


